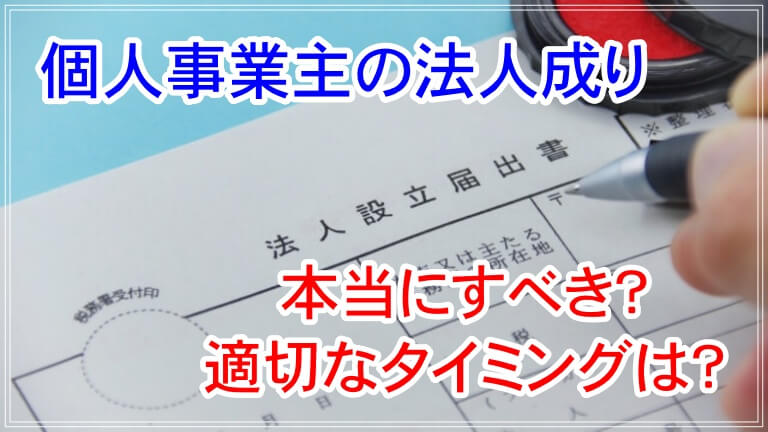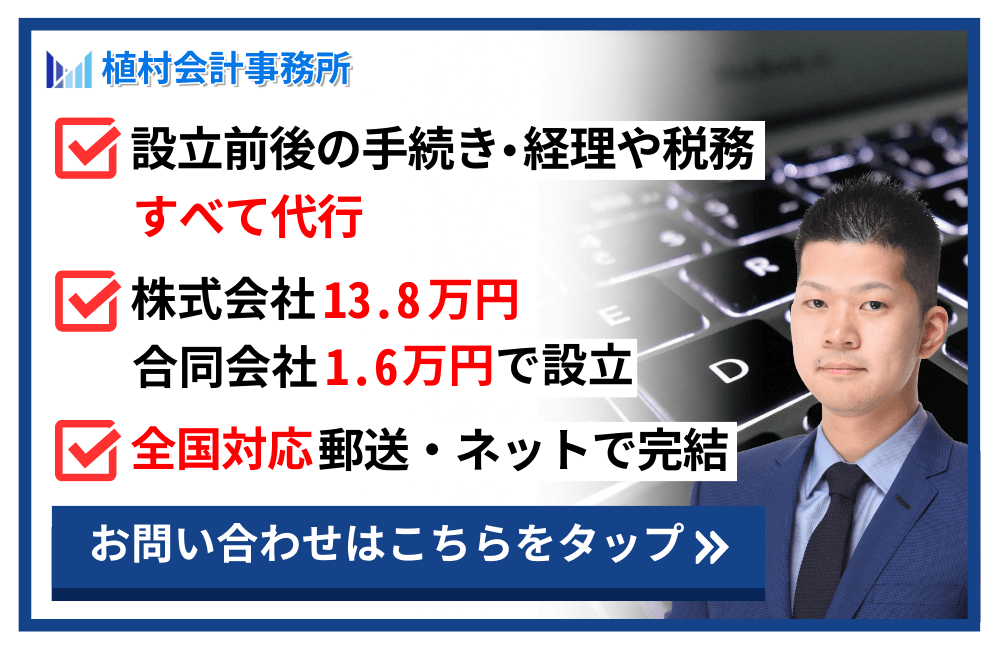こんにちは、法人成りの対応実績が豊富な税理士の植村拓真です。
個人事業主で事業が順調な方であれば、そろそろ法人成りを検討しているのではないでしょうか。
法人成りには節税効果や信用度の向上など、さまざまなメリットがあります。
【法人成りのメリット】
信 事業の信用
金 資金調達
税 税率の差
所 所得の分散
退 退職金支給の経費
相 相続、事業承継の課税対象
損 純損失の繰越年数シンキンゼイショタイソウソン❗️#FP1級
— たかやん@資格受験アカ (@study_taka3) September 16, 2019
とはいえ、中には

と悩んでいる方もいるかと思います。
今回はそんな方に向けて、個人事業主の法人成りとは何かから、メリット・デメリットとあわせて解説します。
また、どんな方が法人成りすべきかを注意点とあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも個人事業主の法人成りとは?

法人成りとは、個人事業主が新たに株式会社や合同会社などを設立して、事業を引き継ぐことです。
個人の資産と負債を新設会社に引き継いで、事業を継続します。
そして、預金や固定資産だけでなく、買掛金や未払金なども引き継ぎます。
そんな法人成りですが、平成18年に会社法が大幅に改正されたことで行いやすくなりました。
- 最低資本金規制の撤廃
→1円起業が可能に・会社役員の人数の規制緩和
→非公開会社なら取締役一人でもOK
最低資本金の規制が撤廃される前は、有限会社で最低300万円・株式会社で最低1,000万円の資本金が必要でした。
さらに、会社役員は取締役3人と監査役1人が必要でした。
今でこそ資本金1円で一人会社を設立する方は珍しくありませんが、会社法改正前は気軽に法人成りできなかったのです。
法人成りする際の大まかな流れは、以下のとおりです。
↓
②個人事業主の資産と負債を新設会社に引き継ぐ
↓
③法人として事業を継続する
通常の会社設立とは異なり、個人事業主時代の資産・負債を引き継いだうえで事業を継続します。
そして、法人成りと通常の会社設立とでは、かかる費用と時間も異なります。
法人を設立するためにかかる費用(法定費用)の目安は、以下のとおりです。
| 内訳 | かかる費用 |
| 公証人へ払う認証手数料 | 5万円 |
| 定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (1部につき250円、必要部数によって異なる) |
| 定款に貼付する収入印紙代 (電子定款の場合は不要) |
4万円 |
| 登録免許税 | 15万円 (大抵の場合) |
| 合計 | 約24万円 |
株式会社を設立するには、約24万円の法定費用と約2週間の時間がかかります。
一方、個人事業主の開業手続きは、税務署に開業届などを届け出れば完了します。
法人成りの手続きに比べると低コストで簡単ですし、時間がかかりません。
ではなぜ、個人事業主の方が法人成りを検討するのかといえば、さまざまなメリットがあるからですね。
法人成りのメリットについては、『個人事業主が法人成りする4つのメリット』の項目で詳しく解説します。
個人事業主と法人の違い
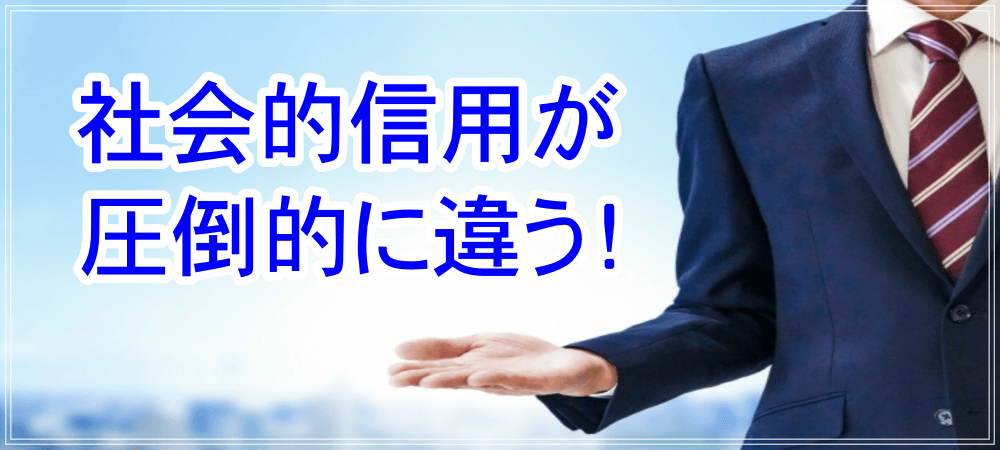
個人事業主と法人の違いについて、簡単にお話しておきます。
法人成りのメリット・デメリットに関する内容なので、確認しておきましょう。
個人事業主と法人の大きく異なる点は、以下のとおりです。
- 会社設立の手続き
- 社会的信用
まず会社設立の手続きですが、個人事業主は税務署に開業届を提出すれば完了します。
一方、法人は約20万円の費用がかかり、設立までに2週間程度かかります。
では、なぜ法人成りする個人事業主がいるのかというと、社会的信用が得られるからです。
会社設立・維持のコストを負担しているため、本気で事業をしている会社だと信用されやすくなります。
法人成りするためには、会社設立費用に加えて維持費も必要です。
住民税の均等割、社会保険料、税理士報酬など、売上がなくても数十万円かかってしまいます。
維持費を支払えるほど売上が伸びているか事業に本腰を入れていなければ、法人成りは検討しませんよね。
ですので、社会的信用を得られるわけです。
個人事業主と法人の違いについては、以下の記事で詳しくお話しています。
関連記事:【法人と個人事業主の違い】メリット・デメリットを比較して法人化を検討
それでは法人成りの具体的なメリットについて、次の項目で詳しく見ていきましょう。
個人事業主が法人成りする4つのメリット
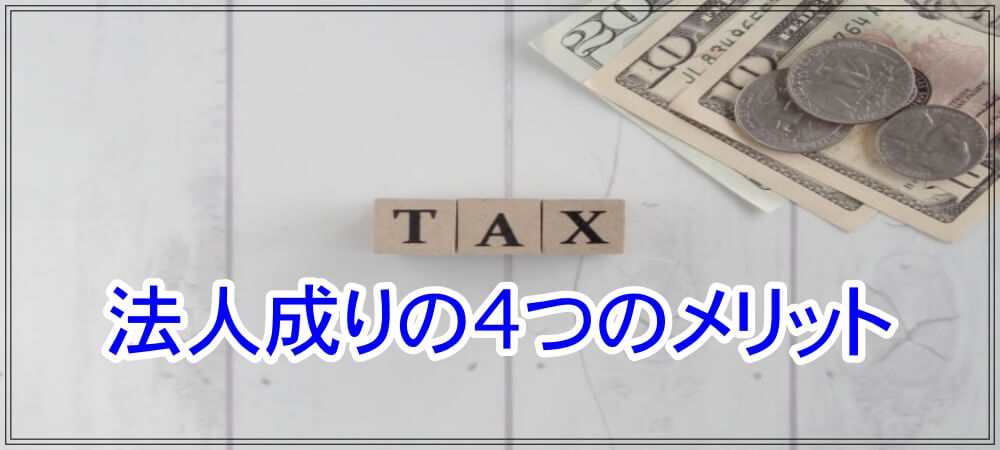
個人事業主の方がお金と時間をかけてまで法人成りする理由は、以下のとおりです。
- 信用されやすくなる
- 節税につながる
- 有限責任になる
- 事業を継承できる
本項目では、上記のメリットについて詳しく解説していきます。
信用されやすい
個人事業主の方が法人成りすると、社会的に信用されやすくなります。
会社設立・維持のコストを負担しているだけでなく、登記簿謄本で重要事項が確認できるからです。
個人事業主の場合は、会社の所在地といった重要事項を登記する必要がありません。
一方、法人は情報がオープンであるため、社会的な信用度が高くなります。
法人でなければ取引しない会社もあるため、法人成りすれば新たな取引先を増やしやすいです。
また、金融機関から融資を受ける際、審査にも通過しやすくなります。
ご自身の事業をさらに大きくしたいなら、法人成りを検討すべきです。
節税につながる
法人成りには節税につながる4つのメリットがあります。
詳しく見ていきましょう。
最長2年間消費税の納付が免除される
法人成りすると、最長2年間消費税の納付が免除されます。
ただし、以下の条件を満たす必要があるので確認しておきましょう。
- 資本金が1,000万円未満である
- 設立1年目の前半6ヶ月で課税売上高が1,000万円を超えない
- 人件費(給与の支払額など)が1,000万円を超えない
- 設立1期目が7カ月以下
法人成りの際に資本金を1,000万円以上に設定すると、設立事業年度から課税事業者となります。
ですので、まずは資本金を1,000万円未満で会社設立しましょう。
そして、課税売上高が法人設立1年目の前半6ヶ月で、1,000万円を超えないようにしてください。
超えた場合は、その事業年度から課税事業者となります。
人件費の支払いが年間1,000万円を超えないようにも注意しましょう。
上記3つの条件を意識して、節税対策してみてください。
ただし、令和5年10月1日に導入されるインボイス制度を考慮しなければなりません。
2年の消費税免税を最大限に活かしたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:インボイス制度とは?法人成りのタイミング・注意点について徹底解説
役員報酬が給与所得控除の対象となる
法人は、社長に支払う役員報酬を経費計上できます。
法人税の対象となる金額は、以下のとおりです。
= 課税対象となる金額
さらに、役員報酬は給与所得控除の対象となるため、55万~195万円の控除(令和2年以降)を受けられます。
役員報酬を二度経費として計上できるのが、法人の大きなメリットです。
退職金を損金として扱える
法人である場合、退職金を損金扱いで経費計上できます。
個人事業主は退職金を経費計上できないため、法人のメリットであるといえます。
ただし、あまりにも高額な退職金は、損金として認められず経費計上できません。
ですので、退職金は会社の在籍期間や役員報酬の金額、功績などを考慮して設定しましょう。
欠損金の繰越控除を10年間受けられる
赤字は翌年以降の事業所得と相殺できます。
個人事業主の場合は、3年間にわたって欠損金の繰越控除を受けられます。
一方、法人成りした場合、欠損金の繰越控除を受けられる期間は10年間です。
大きな赤字を抱えた際、法人は個人事業主よりも6年長く赤字を繰越せます。
法人成りで節税を考えている方は、マイクロ法人も検討してみましょう。
関連記事:【マイクロ法人設立で節税】個人事業主と二刀流のメリット・違法性を解説
有限責任になる
個人事業主は会社が倒産して負債を抱えた際、無限に責任を負う必要があります。
事業に失敗すれば、すべての負債を返済しなければなりません。
一方、法人成りしている場合は責任は有限となります。
つまり、会社が倒産して負債を背負った場合、出資した金額分のみ返済責任を負います。
個人事業主の方は、万が一の事態を考慮して法人成りしておくと良いでしょう。
事業を継承できる
法人成りしておけば、次の社長に事業をそのまま継承できます。
新たに認可を受ける必要がなく、屋号も元のまま使用できるのが法人のメリットです。
個人事業主が事業を継承する場合は、税務署に開業届を出す必要があります。
法務局や税務署などで、一から手続きを行わなければなりません。
さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:法人成りのメリットは責任・信用・節税!デメリットにも注目して検討
個人事業主が法人成りする5つのデメリット

ここまで、個人事業主が法人成りするメリットについてお話しました。
- 信用度の向上
- 節税につながる
- 有限責任
- 事業を継承しやすい
法人成りには、主に4つのメリットがあります。
しかし、メリットだけでなくデメリットもあります。
法人成りのデメリットは、以下のとおりです。
- 社会保険に加入する必要がある
- 設立費用がかかる
- 事務的な負担が増える
- 役員報酬で給与が固定になる
- 赤字でも納税する必要がある
詳しく見ていきましょう。
社会保険に加入する必要がある
個人事業主が法人成りする際、社会保険に加入する必要があります。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことで、加入義務があります。
そして、会社側は社会保険料の半額を負担しなければなりません。
従業員を雇用すればするほど、人数分負担が増えるんですね。
また、社長ひとりの社会保険料だけでも、個人事業主時代の保険料より高額です。
しかし、法人成りしておけば、年金が多くもらえて遺族年金や障害者年金なども充実します。
個人事業主よりも保障が手厚いです。
設立費用がかかる
法人成りで会社を新設する際、どうしても費用がかかってしまいます。
会社設立の際にかかる費用の目安は、以下のとおりです。
| 形態 | かかる費用 |
| 株式会社 | 最低約25万円 (電子定款の場合は約20万円) |
| 合同会社 | 最低約10万円 (電子定款の場合は約6万円) |
大きなデメリットではありませんが、会社設立には約数十万円の費用がかかることを把握しておきましょう。
事務的な負担が増える
法人成りすると、個人事業主時代よりも事務作業が増加します。
そして、作業量が増えるだけでなく、作業内容も複雑化します。
法人税申告書などをご自身で作成するには、税務に関する知識も必要です。
そのため、税理士への依頼を検討している方もいるでしょう。
税理士と契約を交わせば、さらにコストがかかります。
しかし、その分高い節税効果を期待できるだけでなく、煩わしい作業から解放されます。
事務的な負担を減らすためにも、税理士への依頼を検討してみましょう。
法人成りを税理士に依頼する際の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:法人成りを税理士に相談するメリットは?探し方や費用相場とあわせて解説
役員報酬で給与が固定になる
法人成りすると、会社から社長に一定額の役員報酬が支払われます。
そのため、個人事業主のように稼ぎを自由に使えません。
役員報酬は、決算日の翌日から3ヶ月以内に決めた定期同額給与のみ経費と認められます。
決算日の翌日から3ヶ月を超えてから変更すると、経費として認められなくなります。
法人の決算については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【失敗しない】決算期の決め方とは?|意味からいつにすべきかまで徹底解説
法人成りする際は役員報酬を慎重に決定しましょう。
役員報酬の節税効果を最も高める方法について、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ金額を決めるうえで、参考にしてみてください。
関連記事:役員報酬の節税効果を最も高める方法|いくらに設定するべき?
赤字でも納税する必要がある
法人は事業で赤字を出しても、法人住民税の均等割を最低7万円納税しなければなりません。
法人住民税の均等割は、都道府県民税と市区町村民税の2つで構成されています。
都道府県民税の均等割額は、資本金次第で変わります。
一方、区市町村民税の均等割額を決める要素は、資本金だけではありません。
従業員の人数によっても金額が変わります。
以上のとおり、法人住民税の均等割の金額は、会社が赤字であろうと変わりません。
法人は会社の収支が赤字でも、最低7万円の税金がかかると覚えておきましょう。
さらに法人成りのデメリットについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:法人成りのメリットは責任・信用・節税面にあり!デメリットもあわせて解説
個人事業主が法人成りするタイミング
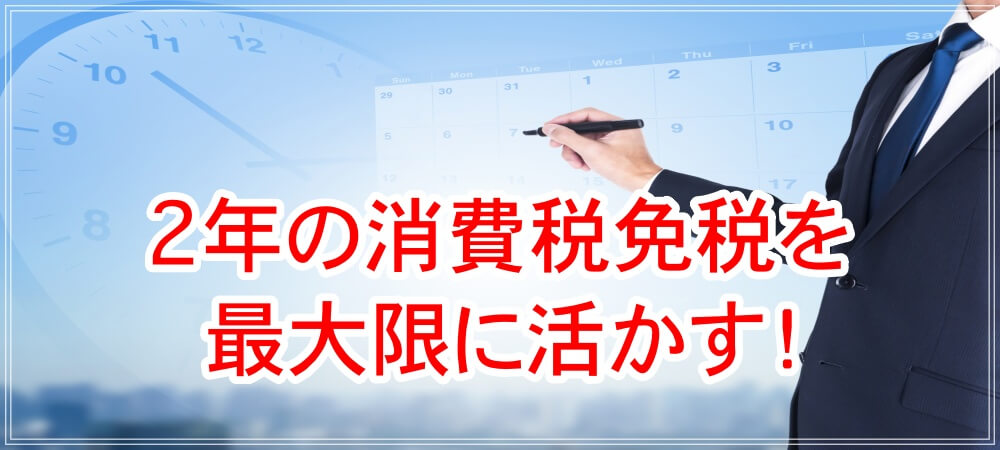
法人成りには、主に4つメリットと5つのデメリットがあるとお話しました。
デメリットがあるといっても、メリットが大きいので検討しておいて損はありません。
それでは、個人事業主が法人成りするベストなタイミングについて解説します。
法人成りする際に意識すべきタイミングは、消費税の課税対象者になる直前です。
個人事業主は
- 2年前の課税売上高
- 設立1年目の前半6ヶ月以内の課税売上高
上記の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。
消費税の納税義務が発生する前に、法人成りを検討してみましょう。
法人と個人事業主は別人格扱いです。法人成りしてしまえば、個人事業主時代の売上高は関係なくなります。
ですので、法人成りすることで、最長2年間消費税の納税が免除されます。
消費税の課税対象者となる前に、法人成りを検討してみましょう。
法人成りによる消費税の免税については、以下の記事で詳しくお話しています。
関連記事:法人成りで消費税の免税事業者になる要件
法人成りのタイミングに関する詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:法人成りのベストタイミングはいつ?後悔しない会社設立時期の選び方
個人事業主が法人成りするための手続き

個人事業主が法人成りするために必要な手続きの流れは、以下のとおりです。
↓
②定款を作成する
↓
③定款の認証を受ける
↓
④代表者個人の口座に資本金を入金する
↓
⑤法務局で設立登記を行う
会社を設立する際、法人成りするからといって特別な手続きは行いません。
通常の株式会社や合同会社を設立すると同じです。
以下のものを用意しましょう。
- 身分証明書(運転免許証など)
- 法人の印鑑
- 発起人の実印
- 定款
- 公証人に支払う手数料(5万円)
- 定款の写し交付手数料(250円×定款のページ数分)
- 収入印紙代4万円分(電子定款の場合は不要)
法人を設立したら、事業にかかわるすべての資産を移行します。
資産を移行する方法には、以下の3種類があります。
| 方法 | 特徴 |
| 売買契約 | 個人事業主と法人で資産を特定して売買する |
| 現物出資 | 個人事業主から金銭を除く資産を現物で出資して、資本金を増加させる |
| 賃貸 | 個人事業主と法人間で賃貸借契約を結び、資産を賃貸する |
また法人成り後は、個人事業主名義のものを法人名義に変更しておきましょう。
会社設立の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:会社設立手続きを自分で行う方法|必要書類と流れを税理士が解説
個人事業主が法人成り後に行う手続き
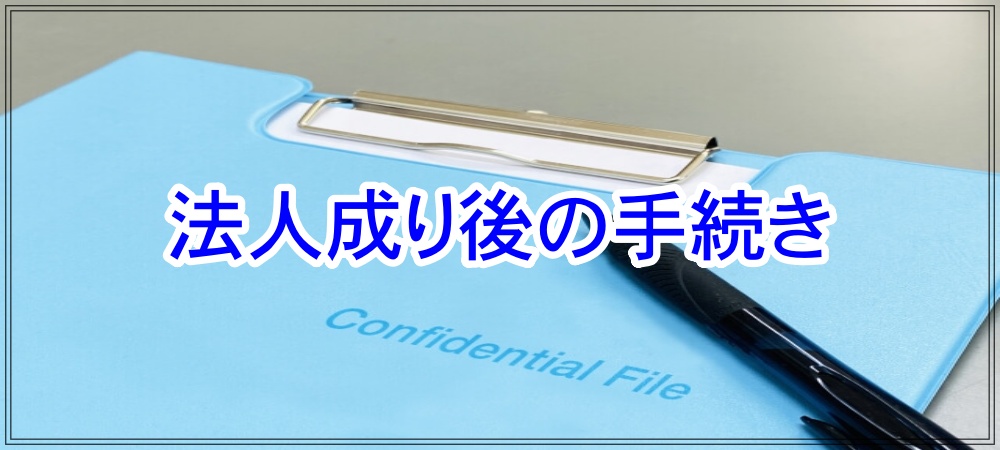
法人成り後は、以下の手続きを行いましょう。
- 税務署に各種届出を行う
- 年金事務所で社会保険の加入手続きを行う
- 労働基準監督署とハローワークに各種届出を行う
- 個人事業主の廃業手続きを行う
- 会社名義の銀行口座を開設する
税務署や都道府県税事務所には、主に以下の書類を提出します。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
そして、年金事務所で社会保険の加入手続きを行う際に提出する書類は、以下のとおりです。
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
法人設立時に従業員を雇用する場合は、
労働基準監督署に
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
ハローワークに
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
上記の書類を提出します。
さらに、個人事業主を廃業する際には、所轄の税務署に個人事業の開業・廃業等届出書、所轄の都道府県税事務所に事業開始(廃止)等申告書を提出します。
また、銀行口座は法人名義で新たに開設して、個人用と法人用で使い分けて管理してください。
個人事業主が法人成りする際の注意点

何かと複雑で作業量の多い法人成りですが、行う際にいくつかの注意点があります。
簡単に以下の内容を解説するので、覚えておきましょう。
- 個人事業主分の確定申告を忘れない
- 廃業後に事業税を納める
- 一人会社でも株主総会・取締役会で意思決定する
- 名義変更の手続きを忘れない
個人事業主分の確定申告を忘れない
まずは、個人事業主分の確定申告を忘れないようにしてください。
個人事業の廃業届を税務署に提出し終えても、油断しないように注意しましょう。
確定申告で申告する内容は、以下のとおりです。
- 廃業前までの申告分
- 法人に資産を移行する際に発生する譲渡所得
- 消費税(課税事業者の場合)
廃業後に事業税を納める
そして、個人事業の廃業から1ヶ月以内に、個人事業税も申告しなければなりません。
個人事業税は、廃業年度分の確定申告時に、事業税の見込額を租税公課として経費計上できます。
経費計上できないと思われがちなので、忘れないようにしましょう。
個人事業税の納税は、確定申告を行った年の8月頃に通知が届いてから行います。
個人事業を廃業したあとではありますが、見込額を経費計上できる特例があります。
一人会社でも株主総会・取締役会で意思決定する
法人が意思決定する際、たとえ一人会社でも株主総会・取締役会を開かなければなりません。
個人事業主のように、自由に意思決定できません。
招集通知・議事録などを作成・保管しておきましょう
名義変更の手続きを忘れない
法人成りが完了したら、個人事業名義で契約しているものを法人名義に変更しましょう。
名義変更するものは、以下のとおりです。
- 賃貸借契約
- クレジットカード
- 電話料金
- 公共料金
など
家賃や電話料金などは、個人名義の口座から引き落とされても経費計上できます。
しかし、個人が法人の料金を立て替えた形になるため、会計処理が複雑になってしまいます。
ですので、法人成りの手続きを済ませたら、名義変更を忘れないようにしましょう。
弊所では、個人事業主の法人成り(新規の会社設立)の手続き代行を承っております。
顧問契約を結んでいただけますと
- お客様の状況をヒアリング
- 無料の節税シミュレーション
など
上記のような内容を実施してしっかりお客様の状況を把握したうえで、法人成りすべきかどうかからご提案させていただきます。
法人成りでお悩みの方は、以下の問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
法人成り・会社設立に関する知識がまったくない方でも大丈夫です。