こんにちは、マイクロ法人の顧問実績が豊富な税理士の植村拓真です。
個人事業主が法人化する際、通常は個人事業の廃業手続きを行って法人一本で事業を行います。
しかし、中には個人事業主と法人を掛け持ちして、税金や社会保険料を抑えようと考える方もいらっしゃいます。
本記事をご覧の方も、同じように考えていらっしゃるのではないでしょうか。
結論から述べますと、個人事業主と法人の掛け持ちはできます。
ただし、条件を守らないと税務調査で租税回避を指摘されかねません。
そこで今回は、個人事業主と法人を掛け持ちするメリット・デメリットについて解説します。
インボイス制度についてご存知でない方は、法人成りするうえで重要な制度ですのでインボイス制度と法人成りに関する記事からご覧ください。
個人事業主と法人は掛け持ちできるが注意点あり
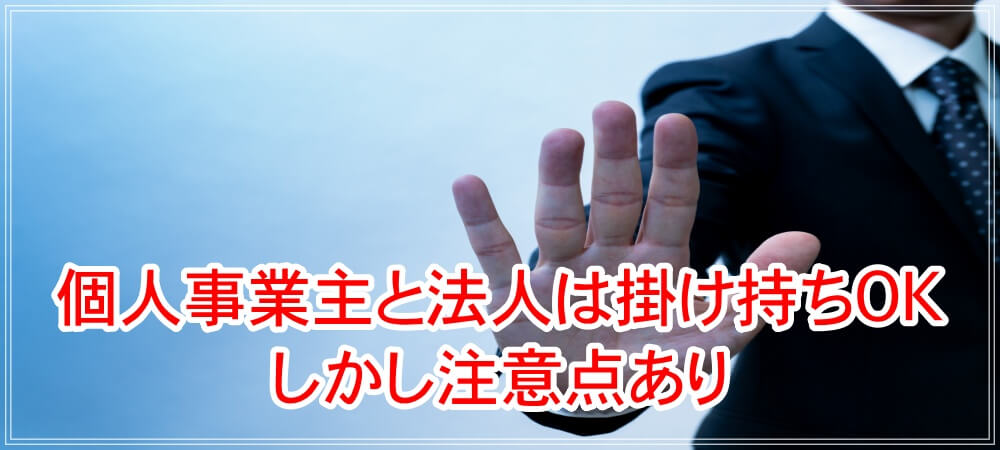
繰り返しになりますが、個人事業主と法人は掛け持ちできます。
しかし、特定の条件を守らなければ税務調査で指摘されてしまいますので、本項目にて注意点を解説しておきます。
個人事業主と法人を掛け持ちする際の注意点は、以下のとおりです。
- 個人事業主と法人で別々の事業を行う
- なるべく個人事業主と法人間で外注費を支払わない
順番に見ていきましょう。
個人事業主と法人で別々の事業を行う
個人事業主と法人を掛け持ちする際は、別々の事業を行いましょう。
同じ事業を行うと売上を調整して税金を抑えられるため、税務署から租税回避を行っていると指摘される恐れがあるからです。
たとえば、個人事業主でアフィリエイター、法人でITコンサルといった明確に異なる事業を選択するのがおすすめです。
個人事業主と法人でブロガーといったように同じ事業を選択すると、税務署から租税回避を指摘されるので注意しましょう。
顧問税理士がいない状態で税務署から指摘されると、すべて自力で対応しなければなりません。
安心かつスムーズに事業を行うためにも、個人事業主と法人を掛け持ちする際は別々の事業を選択しましょう。
なるべく個人事業主と法人間で外注費を支払わない
個人事業主と法人を掛け持ちする際、二者間での外注費の支払いはなるべく行わないようにしましょう。
二者間で外注費の支払いを行えば利益の調整を行えるため、税務調査で指摘される恐れがあるからです。
税務上の疑念を招く恐れがありますので、個人事業主と法人を掛け持ちする際は、なるべく二者間での外注費の支払いによる利益調整を行わないようにしましょう。
個人事業主と法人を掛け持ちするメリット
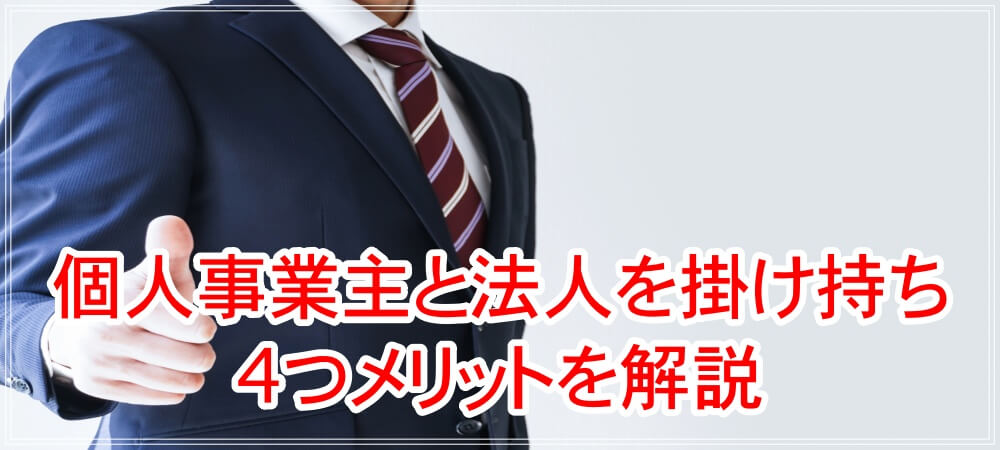
続いては、個人事業主と法人を掛け持ちするメリットについて解説します。
実践するかしないかを判断するうえで、本項目の内容を参考にしてみてください。
- 社会保険料を抑えられる
- 節税効果を高められる
- 法人の対外的な信用の高さを利用できるケースがある
- 利用できる補助金の種類が増える
社会保険料を抑えられる
個人事業主と法人を掛け持ちには、社会保険料を抑えられる大きなメリットがあります。
法人化後に個人事業主を残して併用しようと考える方の多くが、社会保険料の削減を目的にしています。
個人事業主と法人を併用して、法人から安めの役員報酬を個人に支払い、健康保険料と厚生年金保険料を抑えるといったスキームです。
個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入しますが、法人化して会社の役員になれば健康保険や厚生年金に切り替えられます。
そのため、役員報酬の金額を少なく調整すれば、健康保険料や厚生年金の負担額を減少させられます。
上記のスキームを利用すれば社会保険料を抑えられるため、個人事業主を廃業させずに法人と掛け持ちする方がいます。
節税効果を高められる
個人事業主と法人を掛け持ちすれば、各事業形態での税金面におけるメリットを享受できます。
主なメリットは以下のとおりです。
- 個人事業主で青色申告の控除を受けられる
- 売上を分散させて消費税の免税事業者になれる
- 役員報酬を損金算入できる
- 役員報酬の給与所得控除を受けられる
- 出張手当などの法人のみの節税対策を実施できる
上記のとおり、個人事業主と法人両方の節税対策を実施できるため、節税効果を高めて手元により多くの資金を残せます。
必ずしも個人事業主と法人の併用が正解とは限りませんが、しっかりとシミュレーションを行えば税金面でメリットを享受できます。
法人の対外的な信用の高さを利用できるケースがある
法人は個人事業主よりも対外的な信用が高いため、法人化すると対外的な信用が高まります。
そして、個人事業主と法人を掛け持ちすれば、個人事業を行いながら法人の対外的な信用の高さを利用できます。
個人事業主が法人の対外的な信用の高さを利用する主なメリットは、以下のとおりです。
- リクルートのハードルが下がる
- 資金調達の審査で有利になる
- 新規取引先の開拓につながる
- 法人名義なら保証人なしで事務所を借りられるケースがある
法人の肩書きをうまく活用すれば、人材確保や資金調達、新規取引先の開拓や事務所の契約で有利です。
ただし、個人事業主と法人間で売上を調整して節税する場合、売上の減少により審査で不利になる恐れがあります。
そして、通常は法人化後に個人事業を残すメリットがないため、審査で掛け持ちする理由を説明できなければ節税目的であると見なされて印象が悪くなり、落ちる恐れがあるので注意しましょう。
利用できる補助金の種類が増える
個人事業主と法人を掛け持ちすれば、各事業形態向けの補助金を受給できます。
本来であればどちらかの補助金は受給できませんが、掛け持ちしていれば両方を受給できますのでうまく活用しましょう。
個人事業主と法人にはどんなメリットとデメリットがあるのかについては、以下の記事で比較を紹介しています。
併用するとどんなメリットを享受できるのかについてご覧ください。
関連記事:【法人と個人事業主の違い】メリット・デメリットを比較して法人化を検討
個人事業主と法人を掛け持ちするデメリット
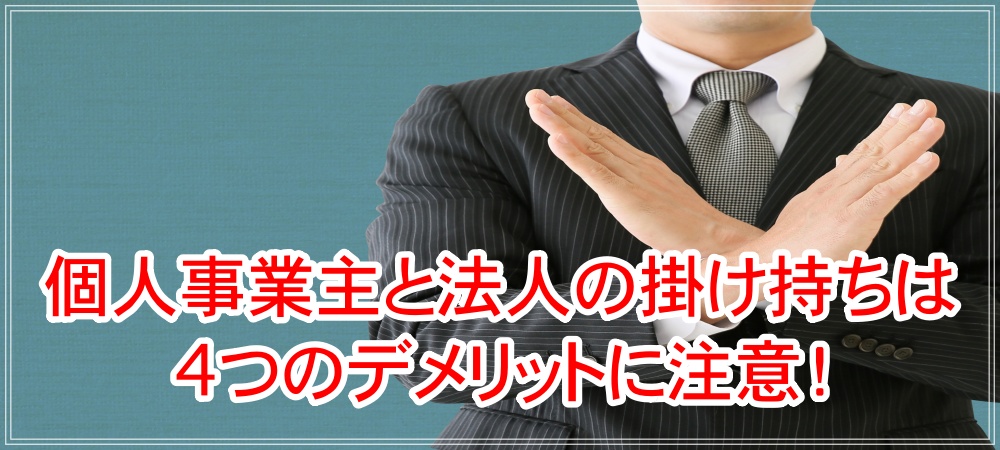
続いては、個人事業主と法人を掛け持ちするデメリットについて解説します。
以下のようなデメリットがあるので、掛け持ちする際は注意しましょう。
- 個人事業主と法人の両方で税金を納める必要がある
- 法人の経理や税務会計が必要で手間が増える
- 法人では社会保険の加入が必要である
- 売上規模が小さくなる
個人事業主と法人の両方で税金を納める必要がある
個人事業主と法人を掛け持ちする場合、両者で税金を納めなければなりません。
個人事業主の所得税や住民税、事業税はもちろん、法人の法人税や住民税、事業税も納める必要があるため、申告作業に時間がかかります。
個人事業主と法人を掛け持ちするとひとりで事業者2人分の申告が必要ですので、事業に集中できない恐れがあります。
さらに、正確に申告しなければ税務署から指摘される恐れもありますので、正確な申告や税務調査の対応などが不安な方は税理士への依頼を検討してみましょう。
法人の経理や税務会計が必要で手間が増える
個人事業主と法人を掛け持ちすると、両者で経理や税務会計を行う必要があります。
法人化後に個人事業を残して事業を行うため、法人一本で事業を行うよりも手間が増えてしまうのは仕方ありません。
個人事業主の経理や税務会計であれば、自力で行える方もいらっしゃいます。
しかし、法人の経理や税務会計は個人事業主よりも複雑かつ作業量が多いため、自力ですべてを行うのは困難です。
個人事業主と法人を掛け持ちする際は両者の経理や税務会計を行う必要があるため、専門知識を有したうえである程度の経験がなければ自力では行えないでしょう。
また、法人化するには会社設立の手続きも行う必要があり、決算期や役員報酬といった重要な要素や手続きの期限など、考えなければならない内容が多いです。
税務調査の対象になる恐れもありますので、安心してスムーズに事業を行いたい方は税理士への依頼を検討してみましょう。
【全国対応】個人事業主と法人の掛け持ちに関するご相談はこちら
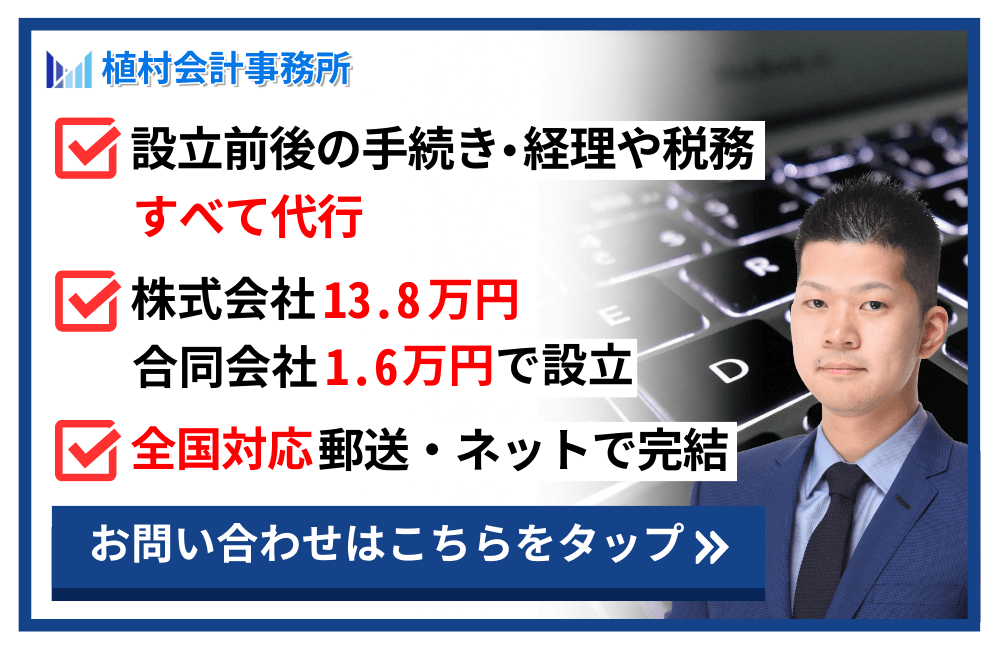
法人では社会保険の加入が必要である
法人は社会保険に加入する義務があるため、個人事業主と法人を掛け持ちする際は社会保険料分の負担が増えます。
そして従業員を雇用する際は、社会保険料の半分を会社側が負担しなければなりません。
個人事業主と法人を掛け持ちする際は一人社長の会社を設立するケースが多いですが、ひとりでも社会保険に加入する義務はありますので注意しましょう。
売上規模が小さくなる
個人事業主と法人を掛け持ちして売上調整を行うと、両者で売上規模が元より小さくなってしまいます。
分割するため仕方ありませんが、融資や助成金などの審査で不利になるケースもありますので注意しましょう。
将来受け取れる年金が減額されてしまう
個人事業主と法人を掛け持ちすると、厚生年金保険料の負担を軽減させられるメリットを享受できます。
一方で厚生年金保険料の負担軽減により、将来受け取れる年金が減額されてしまうので注意しましょう。
以上が個人事業主と法人を掛け持ちする際のデメリットです。
個人事業主と法人を掛け持ちするかどうかを判断するうえで、参考にしてみてください。
【全国対応】個人事業主と法人の掛け持ちについて税理士に相談する
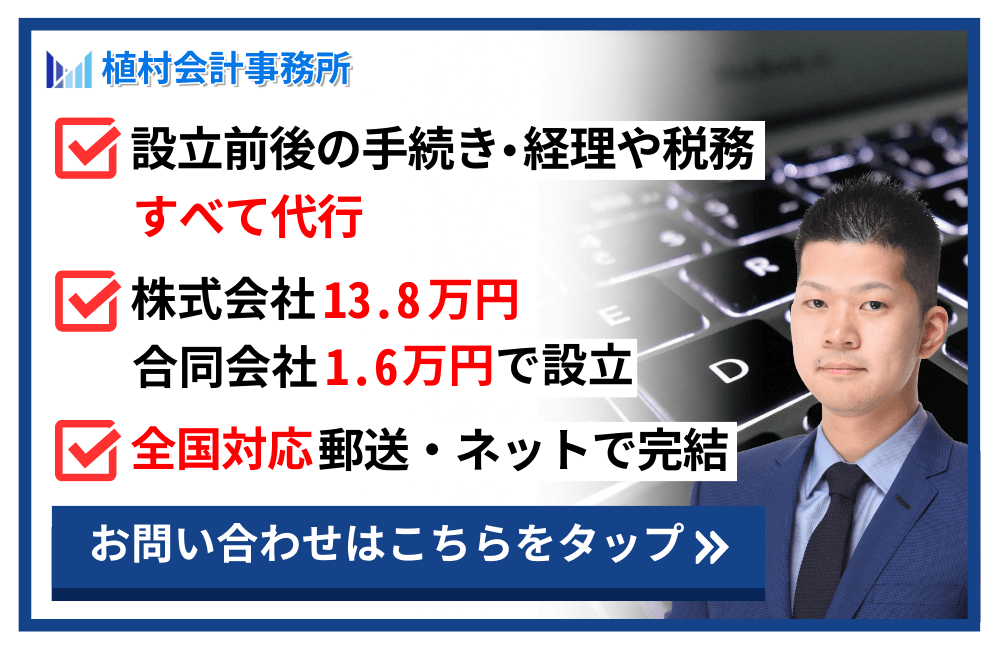
よく個人事業主と掛け持ちされるマイクロ法人とは?

最後に、個人事業主と法人を掛け持ちする際に用いられるケースが多いマイクロ法人について解説しておきます。
マイクロ法人の主な特徴は、以下のとおりです。
- 税金や社会保険料を抑えるために設立する
- 従業員を雇わず社長ひとりで経営する
マイクロ法人とは、フリーランスの個人事業主や副業のサラリーマンが主に税金や社会保険料を抑えるために設立する法人のことです。
税金や社会保険料を抑える目的で設立されていますので、従業員を雇わずに一人社長が経営する傾向があります。
そして、マイクロ法人は税金や社会保険料を抑える目的で設立される傾向があるため、株式会社よりも設立費用や維持費が安い合同会社を選択する方が多いです。
マイクロ法人の具体的なメリットやデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:【マイクロ法人設立で節税】個人事業主と二刀流のメリット・違法性を解説
個人事業主と法人を併用すべきかお悩みの方はお気軽にご相談ください

今回は個人事業主と法人を掛け持ちするメリット・デメリットについて解説しました。
個人事業主と法人を掛け持ちする際は、事業形態ごとに別々の事業を選択する、なるべく外注費の支払いを控えるといった点に注意しましょう。
そして、法人設立後の経理や税務会計の負担増加、将来受け取れる年金が減額されてしまう点には、特に注意して事業を行ってください。
個人事業主と法人を掛け持ちするうえで不安がある、掛け持ちすべきか法人一本でいくべきか迷っていらっしゃる方は、お気軽に弊所までご相談ください。
弊所は個人事業主と法人を掛け持ちしている方の顧問実績が豊富ですので、お力になれると存じます。

